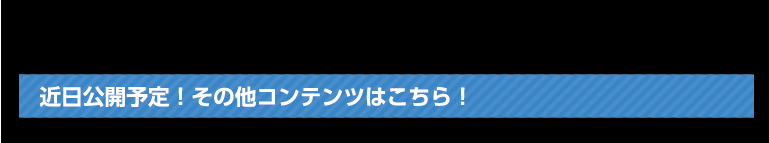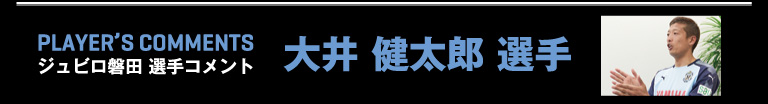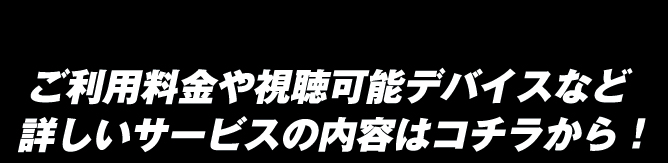提供:DAZN for docomo

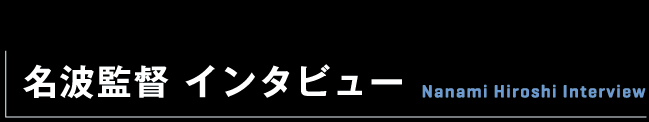
DAZN for docomoを実際にジュビロ磐田での チームづくりにも活かしている名波監督。
ジュビロ磐田でのDAZN for docomo活用法
――普段、DAZN for docomoで放映しているjリーグや海外サッカーを観られることはありますか?
もちろんです。おそらくJ1、J2の40クラブの監督の中では5本の指に入るんじゃないかと自負しているくらい、観ています。チームづくりにおける活用法としては、自チームの試合終了後、2時間以内には必ず一度、試合を見返し、そのあとにもう一回観て、「GOODシーン」「BADシーン」を120項目ほど切り取り、例えば「GOOD、10番、積極的なシュートシーン」などと書き出して選手にフィードバックすることで、僕がどういう「GOODシーン」「BADシーン」を選んだのかを知ってもらうようにしています。また、対戦相手のスカウティングのためにも活用します。コーチングスタッフ、分析担当とともに、相手チームが今年に入って戦った公式戦を見返し、どこがストロングポイントでどこがウィークポイントなのかを探して選手にフィードバックするのもその1つです。
――選手の皆さんにチームスタイルを落とし込んでいく上で、似たようなスタイルを嗜好している海外チームの映像を観せることはされますか?
このチームを、っていうのはないですが、このシーンやあのシーンっていうことでは、たくさんあります。例えば、17-18シーズンのプレミアリーグ、『ハダースフィールドVSマンチェスター・ユナイテッド』戦で、マンチェスター・ユナイテッドのFWルカク選手(ベルギー代表)が0-2で負けている状況で、一人でハーフウェーラインくらいから右サイドの深いところまでドリブルで持ち上がったシーンがあったんです。ゴールラインまであと2〜3メートルの距離だったのでそこで相手選手に当てればコーナーキックになったのですが、ルカク選手は0−2で負けている状況だったからか、それをせずに左足でクロスボールを放り込んだ。ゴール前には相手選手が3枚いたのに対して、自チームの選手は1枚しかいないという3:1の状況だったんですけどね。でもそれをFWラッシュフォード(イングランド代表)が決めて1点差に詰め寄った、と。そのシーンをなぜ、僕が切り取ったのかといえば、我々のチームコンセプトに『まずは自分たちが休むな』ということと『相手を休ませるな』というものがあるからなんです。その定義に照らし合わせると、マンチェスター・ユナイテッドは休まずに、つまりはコーナーキックにせずに「まだプレーは続いているんだ」という意思を見せた、と。その上で、タイミングよくクロスボールを放り込んだことでGKも含めれば1:4の数的不利な状況だったのにゴールを決められた。だからこそ、そのシーンを選手に提示して「これこそが、俺たちが目指そうとしているサッカーの答えだぞ」と伝えました。そうした映像の利用方法以外にも、例えばゴールシーンを観る際に、そのゴールがどういう流れで生まれたのかを知るために、フルマッチを観た上で、再度ゴールシーンの1分前くらい前から再生して「このゴールはクリアミスから生まれたんだ」とか「ショートパスの連続から味方が動き出す時間を作ったことで、このゴールシーンに繋がったんだ」ということを確認することもあります。
――そうやって選手の皆さんに『観る』ことで意識づけしていくことによって、プレーでの変化も感じられますか?
そう思います。実際、選手もその手応えがあるから、僕が特に何かを言わなくても自発的に試合前のバスの移動中にずっと観ていたり、選手によっては試合の本当に直前まで…10分前くらいまでタブレットで映像を観ている選手がいるんだと思います。そういう意味ではイメージを膨らませることも含めて非常にDAZN for docomoは役に立っています。もっともそんな風にプレーや自分たちのサッカーの質をより高めるためだけではなく、単に『サッカー』を楽しみたいという思いでDAZN for docomoを活用している選手もいるはずですが。
もちろんです。おそらくJ1、J2の40クラブの監督の中では5本の指に入るんじゃないかと自負しているくらい、観ています。チームづくりにおける活用法としては、自チームの試合終了後、2時間以内には必ず一度、試合を見返し、そのあとにもう一回観て、「GOODシーン」「BADシーン」を120項目ほど切り取り、例えば「GOOD、10番、積極的なシュートシーン」などと書き出して選手にフィードバックすることで、僕がどういう「GOODシーン」「BADシーン」を選んだのかを知ってもらうようにしています。また、対戦相手のスカウティングのためにも活用します。コーチングスタッフ、分析担当とともに、相手チームが今年に入って戦った公式戦を見返し、どこがストロングポイントでどこがウィークポイントなのかを探して選手にフィードバックするのもその1つです。
――選手の皆さんにチームスタイルを落とし込んでいく上で、似たようなスタイルを嗜好している海外チームの映像を観せることはされますか?
このチームを、っていうのはないですが、このシーンやあのシーンっていうことでは、たくさんあります。例えば、17-18シーズンのプレミアリーグ、『ハダースフィールドVSマンチェスター・ユナイテッド』戦で、マンチェスター・ユナイテッドのFWルカク選手(ベルギー代表)が0-2で負けている状況で、一人でハーフウェーラインくらいから右サイドの深いところまでドリブルで持ち上がったシーンがあったんです。ゴールラインまであと2〜3メートルの距離だったのでそこで相手選手に当てればコーナーキックになったのですが、ルカク選手は0−2で負けている状況だったからか、それをせずに左足でクロスボールを放り込んだ。ゴール前には相手選手が3枚いたのに対して、自チームの選手は1枚しかいないという3:1の状況だったんですけどね。でもそれをFWラッシュフォード(イングランド代表)が決めて1点差に詰め寄った、と。そのシーンをなぜ、僕が切り取ったのかといえば、我々のチームコンセプトに『まずは自分たちが休むな』ということと『相手を休ませるな』というものがあるからなんです。その定義に照らし合わせると、マンチェスター・ユナイテッドは休まずに、つまりはコーナーキックにせずに「まだプレーは続いているんだ」という意思を見せた、と。その上で、タイミングよくクロスボールを放り込んだことでGKも含めれば1:4の数的不利な状況だったのにゴールを決められた。だからこそ、そのシーンを選手に提示して「これこそが、俺たちが目指そうとしているサッカーの答えだぞ」と伝えました。そうした映像の利用方法以外にも、例えばゴールシーンを観る際に、そのゴールがどういう流れで生まれたのかを知るために、フルマッチを観た上で、再度ゴールシーンの1分前くらい前から再生して「このゴールはクリアミスから生まれたんだ」とか「ショートパスの連続から味方が動き出す時間を作ったことで、このゴールシーンに繋がったんだ」ということを確認することもあります。
――そうやって選手の皆さんに『観る』ことで意識づけしていくことによって、プレーでの変化も感じられますか?
そう思います。実際、選手もその手応えがあるから、僕が特に何かを言わなくても自発的に試合前のバスの移動中にずっと観ていたり、選手によっては試合の本当に直前まで…10分前くらいまでタブレットで映像を観ている選手がいるんだと思います。そういう意味ではイメージを膨らませることも含めて非常にDAZN for docomoは役に立っています。もっともそんな風にプレーや自分たちのサッカーの質をより高めるためだけではなく、単に『サッカー』を楽しみたいという思いでDAZN for docomoを活用している選手もいるはずですが。

名波監督の実体験から学ぶ、観ることで上達するサッカー
――ご自身も幼少期や選手時代に『観る』ことでサッカーを学ぶことはありましたか?
そうですね。当時は今の時代とは違い、映像自体は少なかったのですが、自分のプレーが映っているテレビ中継を始め、ワールドカップやヨーロッパのサッカーチームの試合など、ビデオ録画できるときは必ず録画して、VHSのビデオテープに撮り溜めて観ていました。また、プロになってからも自分の調子が悪かったり、落ち込んだりした時には必ず実家に戻って、清水商業高校時代(現 清水桜が丘高等学校)、自分が一番輝いていた試合のビデオを見返すのも習慣でした。
――現役時代に海外のサッカーを観る際、ご自身が理想とするサッカーをしているチームや選手を重点的に観ることもありましたか?
海外の試合はそういう観点より、単純に「このゲームはビッグマッチだから観よう」とか、特にこれと決めずに、寝転んで映像を垂れ流して観ることが多かったのですが、その中から、自然と自分のプレーのアイデアに変わることもあったように思います。そのせいか、監督になった今は、選手に対しても「観る」ことをプレーのアイデアにつなげてくれたらいいなという考えから、クラブハウスでいろんな試合の映像を観ている時に「これだ」というものがあれば、分析担当のスタッフを呼んで「この試合の●分●秒を切り取って保存しておいてくれ」とお願いし、それを後々活用することもあります。
――現役時代『観る』ことでプレーが変わったな、という成功体験はありますか?
僕のサッカーの全ては、真似ることがスタートだったと思います。例えば、子どもの頃なら憧れの選手と同じスパイクを履きたいとか、ああいう短パンの履き方をしてみようとか。靴の結び方やソックスのずらし方など、外的な要素から一流選手に憧れました。そこから「すごいシュートを打ったな!」「俺も真似してみよう!」「あのパスはどうやったら出せるのかな?」といったプレーへの興味に変わっていったというか。ファーストタッチ、ドリブルなど細かなプレーの映像を頭に焼き付けて、それをグラウンドで再現してみることもありました。ただ、今の時代とは絶対的にカメラの台数が違いましたからね(笑)。今の時代はいろんなアングルから撮った映像を観られますし、ましてやそれがスロー再生できたりする分、足首の角度やフリーキックを蹴る前のステップ、歩幅まで真似できるので、今の子供たちがすごく羨ましいです。
そうですね。当時は今の時代とは違い、映像自体は少なかったのですが、自分のプレーが映っているテレビ中継を始め、ワールドカップやヨーロッパのサッカーチームの試合など、ビデオ録画できるときは必ず録画して、VHSのビデオテープに撮り溜めて観ていました。また、プロになってからも自分の調子が悪かったり、落ち込んだりした時には必ず実家に戻って、清水商業高校時代(現 清水桜が丘高等学校)、自分が一番輝いていた試合のビデオを見返すのも習慣でした。
――現役時代に海外のサッカーを観る際、ご自身が理想とするサッカーをしているチームや選手を重点的に観ることもありましたか?
海外の試合はそういう観点より、単純に「このゲームはビッグマッチだから観よう」とか、特にこれと決めずに、寝転んで映像を垂れ流して観ることが多かったのですが、その中から、自然と自分のプレーのアイデアに変わることもあったように思います。そのせいか、監督になった今は、選手に対しても「観る」ことをプレーのアイデアにつなげてくれたらいいなという考えから、クラブハウスでいろんな試合の映像を観ている時に「これだ」というものがあれば、分析担当のスタッフを呼んで「この試合の●分●秒を切り取って保存しておいてくれ」とお願いし、それを後々活用することもあります。
――現役時代『観る』ことでプレーが変わったな、という成功体験はありますか?
僕のサッカーの全ては、真似ることがスタートだったと思います。例えば、子どもの頃なら憧れの選手と同じスパイクを履きたいとか、ああいう短パンの履き方をしてみようとか。靴の結び方やソックスのずらし方など、外的な要素から一流選手に憧れました。そこから「すごいシュートを打ったな!」「俺も真似してみよう!」「あのパスはどうやったら出せるのかな?」といったプレーへの興味に変わっていったというか。ファーストタッチ、ドリブルなど細かなプレーの映像を頭に焼き付けて、それをグラウンドで再現してみることもありました。ただ、今の時代とは絶対的にカメラの台数が違いましたからね(笑)。今の時代はいろんなアングルから撮った映像を観られますし、ましてやそれがスロー再生できたりする分、足首の角度やフリーキックを蹴る前のステップ、歩幅まで真似できるので、今の子供たちがすごく羨ましいです。

――名波監督の息子さんもサッカーをされているそうですが、息子さんと一緒にDAZN for docomoを観戦されることはありますか?
もちろんあります。試合を観ながら「このプレーはいいね! よくないね」という話になることもありますし、特に会話はせずに流れている映像を一緒に観ているだけの時もあります。また、僕が独り言のように「この選手うまいな〜」とか「右サイドが空いてるのにな」などと言った時に、息子が「何がうまいと思ったの?」「どのタイミングでサイドが空いているのを見ているの?」などとコミュニケーションをとってきたらそれに答えることもありますし、単純に息子の「なぜ今はあっちにボールが出たの?」「なぜ、あの選手は守備をしないの?」といった質問に、僕なりの答えを提示することもあります。ちなみに子供に対して、先に答えを与えすぎたくないという考えから、自分からサッカーについてのアドバイスすることはほとんどありません。息子が聞いてきたら答えるようにしています。
――今の時代はサッカーにまつわるいろんな映像が手軽に観られるようになりました。
子供の頃はそれらの映像をどのように活かせばサッカーの上達につながると思いますか?
ボールに回転がかかっている時は、どういう蹴り方をしているか、など実際のプレーとイコールになるような映像の利用の仕方をして欲しいなと思います。入りの部分は、単純に「あのボレーシュートがすごかった!」「あの距離から、あの角度からゴールが決まるってすごくない?」「俺もあんなプレーをしてみたいよ」っていうところからでいいと思いますが、そこから「でも、あれだけの回転はかけられないよね」「あそこまで届くように蹴れないよね」「どのくらいボールに体重を乗せれば届くようになるのかな」という風に、自分のプレーにイコールづけていくと、体ができていくにつれ自ずと「あの時はこうだったんだ!」という理解が深まるはずなので。またサイドキックやインステップキック、ヘディングなど、1つ1つの基本技術を映像でみて反復練習してもらいたいという考えもありますが、スーパーなプレーにも憧れる年頃でもあるので(笑)、それにチャレンジしてみるのもいいと思います。さらに言えば、今の時代はインターネットで『パス』と検索すればパスだけのプレー集が出てきたり、『ドリブル』と検索したら、ドリブルだけを切り取った映像が出てきますからね。それを見た上で、DAZN for docomoで試合の映像を観ながら「この試合にあのドリブルは使えたな」というようなフィードバックをしていくのも、より上級者の利用方法ではないかと思います。
――DAZN for docomoではいろんな国の、いろんなリーグのサッカーが楽しめますが、例えば小学生年代でも、海外選手の『スーパーレベル』のプレーを観ることは必要だと思いますか?
もちろんです。それによって、日本のサッカーとの違いを感じるのも大事ですし、幼少期からヨーロッパなど世界のサッカー先進国のリーグのレベルの高さを痛感しながら『サッカー』と携わっていくことで、世界レベルが目からもインプットされることになりますから。それに脳が反応して体が動き出すことも間違いなくあるはずだし、いろんな映像を楽しめる時代だからこそ、僕たちの子供時代よりそのサイクルが働きやすいんじゃないかと思います。実際、僕が子供の頃はサッカー番組といえば『ダイヤモンドサッカー』(放送日時は地域によって違う)でしたが、その中でピックアップされる試合は時間の都合で前半45分で終わってしまうんです。で、翌週に後半の45分が放映される、と。でも10歳の子供が1週間後に前半45分の内容を覚えているはずがないですからね! …という理不尽な時代でしたが(笑)、今はもちろんそういうことはなくハイライトだけの放送もありますし、見逃し配信で観られなかった試合も観ることができる。そういう意味ではそれぞれのライフスタイルにあわせて楽しめるので本当に…先ほども言いましたが、今の子供たちはいいなって思います。
もちろんあります。試合を観ながら「このプレーはいいね! よくないね」という話になることもありますし、特に会話はせずに流れている映像を一緒に観ているだけの時もあります。また、僕が独り言のように「この選手うまいな〜」とか「右サイドが空いてるのにな」などと言った時に、息子が「何がうまいと思ったの?」「どのタイミングでサイドが空いているのを見ているの?」などとコミュニケーションをとってきたらそれに答えることもありますし、単純に息子の「なぜ今はあっちにボールが出たの?」「なぜ、あの選手は守備をしないの?」といった質問に、僕なりの答えを提示することもあります。ちなみに子供に対して、先に答えを与えすぎたくないという考えから、自分からサッカーについてのアドバイスすることはほとんどありません。息子が聞いてきたら答えるようにしています。
――今の時代はサッカーにまつわるいろんな映像が手軽に観られるようになりました。
子供の頃はそれらの映像をどのように活かせばサッカーの上達につながると思いますか?
ボールに回転がかかっている時は、どういう蹴り方をしているか、など実際のプレーとイコールになるような映像の利用の仕方をして欲しいなと思います。入りの部分は、単純に「あのボレーシュートがすごかった!」「あの距離から、あの角度からゴールが決まるってすごくない?」「俺もあんなプレーをしてみたいよ」っていうところからでいいと思いますが、そこから「でも、あれだけの回転はかけられないよね」「あそこまで届くように蹴れないよね」「どのくらいボールに体重を乗せれば届くようになるのかな」という風に、自分のプレーにイコールづけていくと、体ができていくにつれ自ずと「あの時はこうだったんだ!」という理解が深まるはずなので。またサイドキックやインステップキック、ヘディングなど、1つ1つの基本技術を映像でみて反復練習してもらいたいという考えもありますが、スーパーなプレーにも憧れる年頃でもあるので(笑)、それにチャレンジしてみるのもいいと思います。さらに言えば、今の時代はインターネットで『パス』と検索すればパスだけのプレー集が出てきたり、『ドリブル』と検索したら、ドリブルだけを切り取った映像が出てきますからね。それを見た上で、DAZN for docomoで試合の映像を観ながら「この試合にあのドリブルは使えたな」というようなフィードバックをしていくのも、より上級者の利用方法ではないかと思います。
――DAZN for docomoではいろんな国の、いろんなリーグのサッカーが楽しめますが、例えば小学生年代でも、海外選手の『スーパーレベル』のプレーを観ることは必要だと思いますか?
もちろんです。それによって、日本のサッカーとの違いを感じるのも大事ですし、幼少期からヨーロッパなど世界のサッカー先進国のリーグのレベルの高さを痛感しながら『サッカー』と携わっていくことで、世界レベルが目からもインプットされることになりますから。それに脳が反応して体が動き出すことも間違いなくあるはずだし、いろんな映像を楽しめる時代だからこそ、僕たちの子供時代よりそのサイクルが働きやすいんじゃないかと思います。実際、僕が子供の頃はサッカー番組といえば『ダイヤモンドサッカー』(放送日時は地域によって違う)でしたが、その中でピックアップされる試合は時間の都合で前半45分で終わってしまうんです。で、翌週に後半の45分が放映される、と。でも10歳の子供が1週間後に前半45分の内容を覚えているはずがないですからね! …という理不尽な時代でしたが(笑)、今はもちろんそういうことはなくハイライトだけの放送もありますし、見逃し配信で観られなかった試合も観ることができる。そういう意味ではそれぞれのライフスタイルにあわせて楽しめるので本当に…先ほども言いましたが、今の子供たちはいいなって思います。